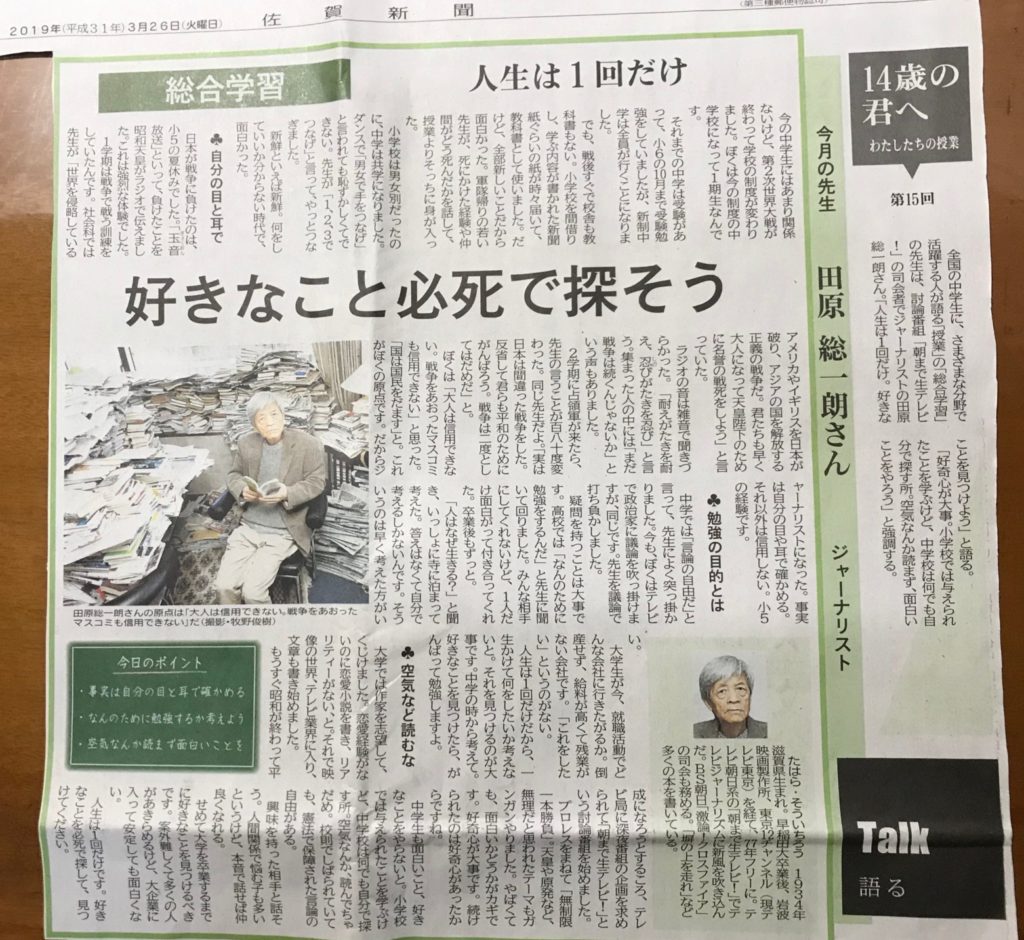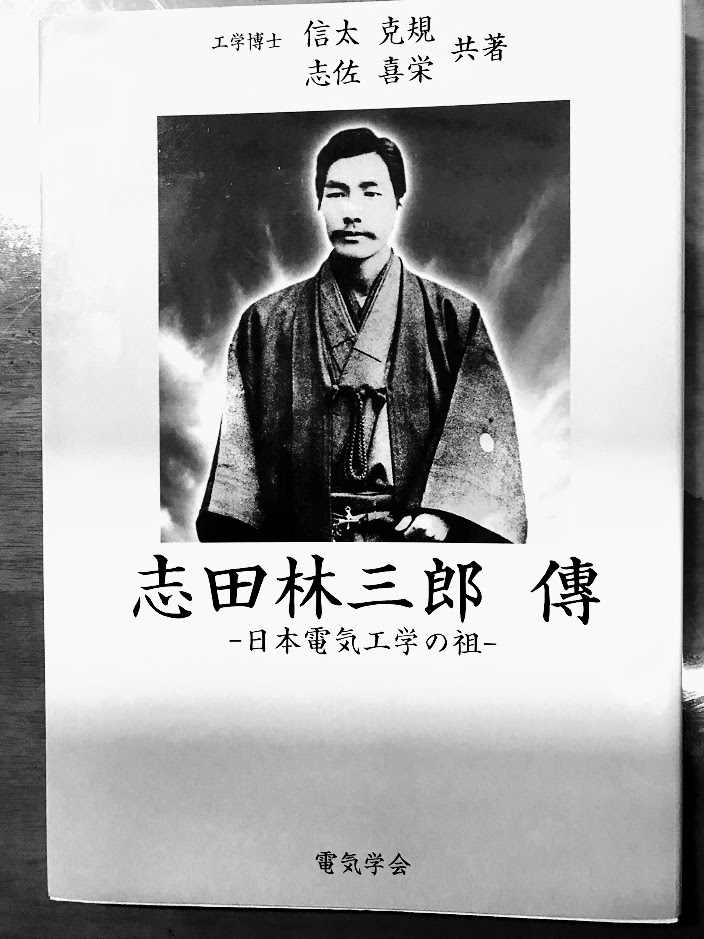わたしは小学、中学までは算数数学という科目は嫌いではなかった。
というより好きだったし、体育と数学は人より優れていた。
しかし、高校数学に入った段階から好き嫌いとは別の感情に覆われてしまったように思う。
それはどうしても理解できないから諦めてしまうという挫折感を味わったのだと思う。
高2のとき文系理系のクラス分けがあり、文系に入らざるを得なかった頃から、自分は文系人間で
化学、物理。数学は不得意科目で理解できないものだとレッテルを張ってしまったのだと思う。
私たちの学年は6クラスあり6組が理系クラスで秀才、後のクラスは文系で強いて言えば数学を必要としない
学部大学を目指すクラスとなったのではなかろうか。この分断された世界は未だに尾を引いている。
当時の経済学部を専攻しようと思うものは文系の世界に属していたと思う。今、思えば何故だろうと思う。
世間の風潮が経済学部に進学するときは数学は必要ないと考えられていたのだろうか?
確かに、私は大学入試試験には数学が必要なく経済学部に入学できたのです。
大学に入っても数学は必要ではなかったことを思い出します。記憶に残っているとしたら、サムエルソンの「経済学」
という分厚い上下2冊の本や経済史の授業、行列式を使った経済数学科目もあったとは思いますが、学部全体を眺めてみると
「マル経」「近経」に分かれていたようです。そういった世界ですから数学は必須ではなかったのです。
そして、大学を選んだ時と同じように就職にも文系人間が入れる世界の門を叩くことになったのでした。
経済を理解したいとう気持ちはずーと持ち続けていましたから証券会社を選んだのは不思議ではないと思います。
証券会社に入ってからも数学の素養がないからということで仕事に支障をきたすようなことはありませんでした。
私の証券会社時代は、バブル経済をもろに経験することになったのですが、世の中の仕組みをわかるどころではありませんでした。
日々の業務に追われ、流されている自分を横目で見ながらどうすることもできず、数学に出会う機会は全くありませんでした。
そして、私が会社を辞める5、6年前だったと思いますが市場調査部の方だったと思います。その方が講師で「オプション」を
勉強する機会があったのですが、その時に強烈に覚えていることは高校のときに味わった挫折感がトラウマとなっていたのです。
あの数学に対する拒絶感をまた味おうなんてと思いました。いま、考えてみるとこの直感は正しかったと思います。
なんと、「数学」そのものに私は出会ったのですから。
前置きが長くなって申し訳ありませんでした。マネーの正体は「数学」でした。その話に戻りましょう。
高橋洋一先生は『数学を知らずに経済を語るな!』とプラトンが言ったのを捩ったのでしょう、というご本を書かれています。
私のようにド文系人として半世紀あまりを生きてきたものが、言うのもなんですが、あえて言いますと
世の中の仕組みを数学で理解するほうがわかりやすいのではなかろうか?ということです。
経済のしくみをわかりたいという欲求が数学という道具を使って探求できるという感じではないでしょうか。
高橋先生は高校数学ぐらいまでのもので経済を解き明かしているようなことを言われています。
また、最近、読んだ西成活裕先生(渋滞学という学問の確立者)は中学数学までで十分だということを言われています。
突然ではありますが、マネーの話に入ります。「ビットコイン」が誕生したのは、謎の日本人(?)サトシ・ナカモト
の論文がメーリングリストに投稿された、2008年11月1日であるとされています。これは同年9月15日のリーマン・ブラザーズの破綻による
金融危機の連鎖、日経平均が一時7000円を下回ったなど、悪夢のような10月がようやく終わった、
その次の日ということになります。
どうして、経済オンチの日本人が数学の塊とも言っていいほどの「マネー」を誕生させられたのでしょうか?
私は、どうも腑に落ちません。
世界の中の日本を特異な国として見ていた当時の状況がなせる業ではないかと思っています。
現に物理学者にはノーベル賞を受賞しているひとは何人もおられますが、経済学では一人もいないではないですか。このアンバランスを
日本人以外の人が揶揄してつけた名前ではなかろうかと思っています。
私たち日本人は数学という道具を通じて世の中を見るのに不慣れです、というか、教育体制が時代に合っていないのではないでしょうか?
最近は、小学生にも株取引を教えているそうですが、まったくもっておかしなことです。そういう時間があるのならもっと算数や数学
を教えるべきです。なぜ、数学を学ぶのかを理解させるには実社会でどのように数学を使っているのかがわかるようなカルキュラムに
変えてはいかがでしょうか? 小手先の諸策では「金融リテラシー」の普及は望めず、「仏を作って魂入れず」の故事ごとく悪弊が横行する
だけです。この過ちは消費税導入後の経過をみると歴然としています。どうして、私たちの国は何度も同じ過ちを繰り返すのでしょうか?
どうも、世の中のことは自然にあるもので私たちがどうしようもできないものとして諦め、受け入れるのではないでしょうか?
わからないものを安易に肯定し、論理的に物事を考え抜く力がないのではなかろうか。そして、そのことが逆に、見えないものに畏怖の念を持ち、
忌み嫌う風潮を温存させているのではないかと心配しています。
野口悠紀雄先生や髙橋洋一先生は理系の分野から経済へ転身された方々なので、数学の目を通じて世の中を
見ているのだと思います。私の例では何なのですが、高校時代の同年配の方々を推測するには8割がたは文系で
その後の人生で数学に出くわすことは滅多にないのではなかろうか思うのです。また、あったとしても、私と同じように
わからないものには蓋をして見てみないふりをしているのではなかろうかと危惧しています。
私は敢えて言いたいのです。私たちにとって生活に欠かせない「マネーの本質が数学である」ということを!
さあ、どうですか? 見てみないふりは出来ますか? みなさん、できないはずです。一緒に数学にもう一度
勇気をもって出会おうではありませんか!
見てみないふりをすることはもう出来ないでしょう。
最後に、数学を通じて経済を見たとき、今度の消費税増税は絶対にさけるべきです。
我が国の歴史を振り返ると「大東亜戦争」、「バブル崩壊後の失われえた20年」、・・・。
そして、今回の「消費税増税」。何回誤った道を選択すれば気が済むのでしょうか?
これは、ひとえに「数学力」の欠如にほかなりません。